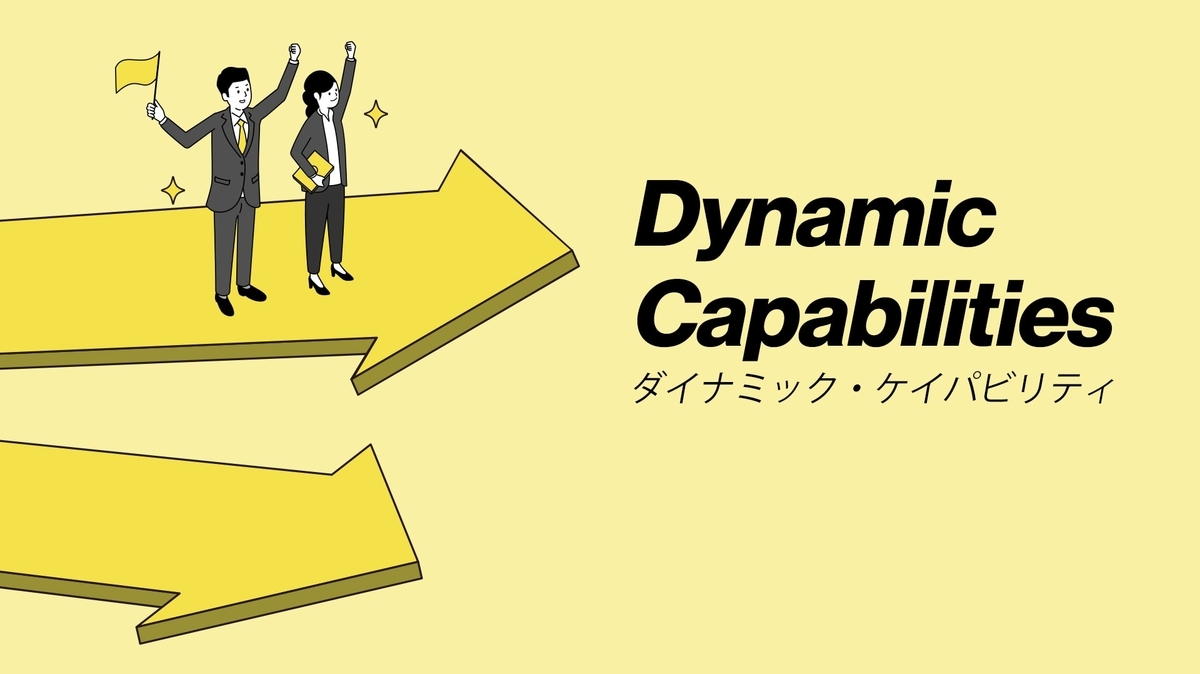
組織のパラダイムシフトは難しいと言われています。
なぜなら、もし既存のパラダイムに問題が発生しても、パラダイム変革をすれば、これまで行ってきた投資が無駄になってしまうからです。それだけでなく、既存のパラダイムに従っていれば当面は得られるはずの利益までもを失ってしまいます。
それで、既存のパラダイムが長期的にみて問題であってもそれを維持するという、非常に不合理な状況に陥ってしまうのです。
真面目さゆえに、一度うまくいくとそのパラダイムを徹底的に精緻化し、そこに莫大な投資をしてしまうため、結果としてパラダイム変革へとシフトしにくくなってしまっている日本企業は少なくないといわれます。
一方、かつて日本の企業が欧米の先進的な企業に追いつき追い抜いたように、現在は中国をはじめとする他国の企業がすぐ背後にまで迫ってきています。
もはやパラダイムシフトなくしては生き残れない時代なのです。
では、企業がパラダイムシフトに関する不条理を回避し、時代の変化に対応して生き延びていくためにはどうしたらいいのでしょうか。
先端的な戦略経営論「ダイナミック・ケイパビリティ論」はその答えを提供してくれます。
ダイナミック・ケイパビリティ―によって成功した企業
ダイナミック・ケイパビリティ―論について説明する前に、実際にダイナミック・ケイパビリティを発揮して成功した企業の取り組みをみてみましょう。
その前に押さえておいていただきたいのは、経済産業省による以下の定義です。
ダイナミック・ケイパビリティとは、環境や状況が激しく変化する中で、企業が、その変化に対応して自己を変革する能力のことである。*1
YKKを襲った「イノベーションのジレンマ」
ここでは、経済学者の菊澤研宗教授の著作から、YKKの戦略についてご紹介します。*2
YKKは現在、世界のファスナー業界で絶対的な地位を確立しています。
ただ、金額ベースでは世界の40%のシェアを誇っているものの、数量ベースでは20%。欧米で製造されている多くのバッグには高品質のYKKのファスナーが使用されていても、市場に出回っているファスナーはほとんどが中国製なのです。
こうした脅威をYKKの経営陣は感知しました。
かつてYKKがアメリカの老舗メーカーの後を追う形で目指したのは、品質のよいファスナー。試行錯誤の結果いきついたのは一貫生産システムでした。紡績、機織り、染色、縫製のすべてを社内で行うことによって、技術水準が高まり、安定した製造と供給も可能になりました。そのため、ファスナーだけでなく、ファスナーを製造する機械も製造してきました。そして、ついにはアメリカの老舗メーカーを追い越して絶対的な地位を築いたのです。
しかし、後発メーカーの影がもうすぐそこにまで迫ってきています。
こうした状況では、「高級なファスナーをいかに安く作るか」という従来のコンセプトが「イノベーションのジレンマ」に陥る可能性を高めているといっていいでしょう。
「イノベーションのジレンマ」とは、高性能な製品を製造・販売し続ける優良な大企業が、より低性能な製品を革新的に製造・販売する新進企業の登場によって淘汰されてしまう状況のことです。
そのための対策は実にシンプル。
ハイエンドの製品(高級品)にこだわらず、ローエンドの製品(低価格品)も作ればいい。いえ、作らなければならないのです。
そのためには、機械製造に関わる技術者がパラダイム変革を起こして、ローエンドなファスナーを製造する機械や材料も作るしかない。
こうした変革は一見、簡単そうに見えますが、実は非常に難しいのです。
それはなぜでしょうか。
YKKは「イノベーションのジレンマ」をどうやって克服しようとしているか
一見、簡単そうなパラダイム変革はなぜ難しいのか。
それは、変革を実現するためには、単にコストダウンするだけではなく、従業員の意識改革も必要だからです。
YKKには成功体験があります。そのため、現状を維持したいという人たち、変化を望まない社員が社内に大勢います。彼らを変化させるためには、人間関係上の非常に高いコストがかかるのです。
特に、技術者にこうした要求をしても、なかなか納得してもらえません。
こうした内部の反発に対して、経営陣は、「ローコスト製品ではなく、高級品でもなく、スタンダード製品を作る必要がある」と、言葉の綾を駆使して説得しています。
これと同じような状況で、変革のためのコストが高いために、長期的な視野を無視して短期的視野を重視し、現状維持に留まっている日本企業があまりにも多いのではないかと菊澤教授は指摘しています。
確かに、社内の抵抗勢力(既得権保有者)との間で生じるコストは莫大なものです。しかし、YKKの経営者陣は、迫りくる危機や脅威にこそチャンスがあると捉えています。
現在、世界のアパレルメーカーは、より安い人件費を求めて中国以外のアジア諸国に縫製工場を移転し始めています。
これまで多くの国でビジネスを展開し、海外でのビジネスパターンやビジネスモデルを確立してきたYKKにとって、そうした環境の変化こそがチャンスなのです。アジア諸国に生産をシフトするアパレルメーカーに、ファスナーを安定的に供給するのはYKKにとっては比較的簡単なことだからです。
そして、そのチャンスを生かすためには、設備投資をし、高級品だけでなくスタンダードな製品を製造する必要があります。
そのために、YKKは社内の技術者を説得する一方で、タイの有名大学と提携して、将来の技術者やエンジニアの育成に投資しています。
このように、会社内外の資産、資源、そして知識を再構成・再配置してイノベーションのジレンマに陥らないように努力しているのです。
特筆すべきは、YKKが単独で利益を独占しようとしていない点です。
YKKは自らを進化させるだけでなく、その地域全体が豊かになるように、ビジネス・エコシステムを形成しようとしています。
企業を成功に導くダイナミック・ケイパビリティ
これまでみてきたYKKの一連の取り組みを可能にしているのが、ダイナミック・ケイパビリティです。
それがどのようなものなのか、みていきましょう。
企業のもつ2つの能力
ダイナミック・ケイパビリティ論は、カリフォルニア大学バークレー校教授のデイヴィッド・J・ティース氏によって提唱された戦略経営論です。*3
ティ―ス教授は、企業のもつケイパビリティ(能力)には次の2つの種類があるといいます。
オーディナリー・ケイパビリティ(通常能力)
ビジネス環境が安定しているとき、企業は既存のビジネスモデルのもとに利益最大化を目標として、コストを削減し、より効率性を高めようとします。このように、企業内の資源をより効率的に扱う企業の通常能力がオーディナリー・ケイパビリティです。
ただ、この能力は、環境や状況に想定外の変化が起きた場合に、どう対応すべきかの答えをもちません。上述のように、ベスト・プラクティスが洗練され、精緻化されていればいるほど、それを変えるコストが高くなってしまいます。したがって、現状維持の方が短期的には経済合理的になるという罠に陥るおそれもあるのです。そのため、自社の強みが弱みに転じ、企業を危機に陥れてしまうこともあります。
ダイナミック・ケイパビリティ(企業変革力)
企業を取り巻く環境は、長期的にみれば大きく変化します。特に現在のように不確実性が高く、変化が激しい時代にあっては、企業は常にそうした変化を感知し、変化に対応して、企業を変革する必要があります。
ダイナミック・ケイパビリティは、オーディナリー・ケイパビリティが生み出す通常の状態と企業を取り巻く環境とが乖離していないかどうかを常に批判的に考察します。そして、新ビジネスの機会を見出し、既存の知識や人材、資産、さらにオーディナリー・ケイパビリティを再構成、再編成する能力です。
先ほどみたYKKの取り組みはその好事例といえるでしょう。
ダイナミック・ケイパビリティの3カテゴリー
ティース教授は、ダイナミック・ケイパビリティを以下の3つのカテゴリーに区分しています。*4
- 感知(sensing):企業の経営陣が競争的状況を把握し、変化や脅威を感知する能力
- 捕捉(seizing):企業の経営陣が、機会を捕捉し、脅威をかわすように、必要に応じて既存の事業や資源、知識を大胆に再構成し、再配置し、再利用する能力
- 変容(transforming):持続的な競争や優位を維持するために、企業の経営陣が企業内外の資産や知識を調整・管理し、ビジネス・エコシステムを形成する能力

経営者の役割は、こうしたプロセスが円滑に回るように采配をふるうことです。
中小企業にこそ勝機がある?
最後に、日本の中小企業は、ダイナミック・ケイパビリティを発揮しやすい環境であるというお話をしたいと思います。
堅固な組織と柔軟な組織
オーディナリー・ケイパビリティをもつ組織は「堅固な組織」であり、逆に高いダイナミック・ケイパビリティをもつ組織は「柔軟な組織」です。*5
「堅固な組織」とは、明確に規定された職務権限がメンバーに与えられている組織です。
このような組織では、各メンバーが産み出す成果も各メンバーに明確に帰属するので、各メンバーは高い成果を出そうと行動します。それが効率性の追求につながるため、オーディナリー・ケイパビリティが高くなる傾向にあるのです。
その反面、新しい生産システムや新しい生産技術を導入しようとすると、全ての職務体系と権限体系を大幅に変化させ、それを各メンバーに再び明確に配分しなければなりません。
上述のように、オーディナリー・ケイパビリティが優位な組織はその変更のためのコストがあまりにも高いため、大きな変革を避けようとする力が働きます。したがって、環境の変化には弱い組織といえます。
一方で、「柔軟な組織」とは、もともと職務権限があいまいな組織です。そのため、組織変革の際に生じるコストが低く、新しい生産システムや生産技術を導入しやすい構造になっています。したがって、このような組織は、強いダイナミック・ケイパビリティをもち、環境の変化に強いのです。
以上のことから、変化の激しい状況では、職務権限をあいまいにしておくような柔軟な組織の方が、強いダイナミック・ケイパビリティを発揮しやすい環境にあるといえます。
中小企業は柔軟な組織
以上のような職務権限の在り方を基準にして、製造業の組織の特徴をアンケート調査した結果が図2です。*6

図2から、大企業はオーディナリー・ケイパビリティが優位な「堅固な組織」の方が多いことがわかります。
一方、中小企業は大企業より「堅固な組織」の割合が少なく、特に「職務権限の内容が明確に規定されている」と答えた中小企業は4割以下、「職位につくための資格要件が明確である」という回答は3割以下でした。
このことから、中小企業の方が、高いダイナミック・ケイパビリティが確保・発揮できる柔軟な組織だといえるのです。
おわりに
現在のように変化が激しい時代にあって、企業がその変化に対応して生き残っていくためには、ダイナミック・ケイパビリティが必須です。
「ダイナミック・ケイパビリティ論」が提供する知見を生かし、もう一度、組織を見直す。そして、必要な変革を模索し見極め、パラダイムシフトに向けて最大限の努力を払う。そこにこそ成功の本質があるのではないでしょうか。
*1:経済産業省「2020年版 製造基盤白書(ものづくり白書):第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題>第1章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望>第2節 不確実性の高まる世界の現状と競争力強化」
*2:菊澤研宗(2019)『成功する日本企業には「共通の本質」がある ダイナミック・ケイパビリティの経営学』朝日新聞出版 Kindle 版 pp.72- 74、pp.76-80、pp.146-148
*3:経済産業省「2020年版 製造基盤白書(ものづくり白書):第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題>第1章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望>第2節 不確実性の高まる世界の現状と競争力強化」
*4:菊澤研宗(2019)『成功する日本企業には「共通の本質」がある ダイナミック・ケイパビリティの経営学』朝日新聞出版 Kindle 版 pp.72- 74、pp.76-80、pp.146-148
*5:菊澤研宗(2019)『成功する日本企業には「共通の本質」がある ダイナミック・ケイパビリティの経営学』朝日新聞出版 Kindle 版 pp.72- 74、pp.76-80、pp.146-148
*6:経済産業省「2020年版 製造基盤白書(ものづくり白書):第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題>第1章 我が国ものづくり産業が直面する課題と展望>第2節 不確実性の高まる世界の現状と競争力強化」

