
東京大学 先端科学技術研究センター 身体情報学分野 教授・博士(工学)
一般社団法人 情報処理学会 理事/情報処理学会誌『情報処理』 前編集長 稲見 昌彦 氏
1960年に設立された一般社団法人情報処理学会。設立以降、めまぐるしく発展する情報処理分野のパイオニアとして、産業界・学界および官界の協力を得て、指導的役割を果たしています。個人会員数は約2万人、情報処理分野において日本最大の学会です。情報処理学会が全会員に毎月配布しているのが、学会誌『情報処理』。情報処理学会の顔でもあります。稲見氏は、2018年から2022年までの2期4年間、編集長として学会誌の改革に取り組んできました。DXもその一つです。今回は稲見氏に学会誌の改革をどのように推進してきたのかお話を伺いました。
※関連ナレッジ資料※
既存製品の提供価値を再定義するバリュープロポジションのつくり方 をダウンロード
マーケティング成果に直結させるGA4分析のポイント をダウンロード
私がまだ博士課程の学生だった頃の話です。「あなたがこの前発表した研究会での研究内容が、山下記念研究賞に選ばれました。」と突然、情報処理学会から電話がかかってきました。その際「稲見さんは会員ではないので、受賞するためには会員になる必要があります。会員になってください。」と言われ、会員になったのです。最初はおめでとう商法かと思いました(笑)。
情報処理学会のことは以前から知っていて、論文や学会誌は読んでいました。当時、たまたま情報処理学会の研究発表会が札幌であって「札幌に行ってみたいな」くらいの気持ちで参加したところ、受賞したのです。研究内容は、後に広く知られるようになった光学迷彩、「透明マント」の基本的なものでした。博士論文にもなり、私が研究者として世に出る機会となりました。
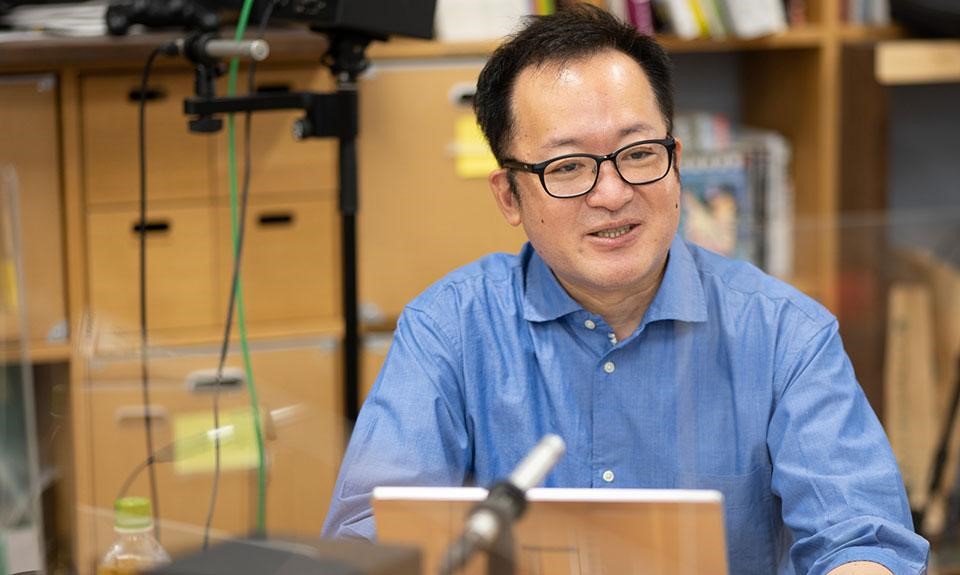
入会してからは、エンターテイメントコンピューティング研究会の立ち上げに関わり、主査をしていました。2000年代には、こうした新しい研究会の立ち上げを行っていました。2015年には、後藤真孝先生が立ち上げた、国際的に活躍する新進気鋭研究者によるトークイベント「IPSJ-ONE」のお手伝いをしました。
その後、当時学会誌『情報処理』の編集長を務めていた塚本昌彦先生から「学会誌の編集、面白いからやってみない?」とお声がけいただきました。まずは副編集長から始めて、2018年に編集長になりました。最初のころは情報処理学会のような巨大で伝統のある学会というのは、変化させるのが難しいと思っていました。しかし、実は新しくできた学会よりも若い人に任せてくれて、懐の深さと新しいものを喜ぶ文化があることに驚きました。これは、IPSJ-ONEに関わったときに感じました。お願いしたことがすべて通ったのです。学会誌の編集も新しいことができると思ったのです。
塚本先生の時代から、女性編集委員を増やすといった取り組みが進められていました。一方で、特集記事の企画がなかなか集まらず行き詰まっていることを課題に感じていました。私が編集長時代に力を入れた1つが、特集記事です。
編集長就任時、学会誌『情報処理』に「編集長就任にあたって 情報処理X」という所信表明記事を書きました。この中で、学会誌の役割を「社会と繋ぐ」「領域を繋ぐ」「世代を繋ぐ」としています。これらを繋げて掛け合わせるという意味を込めて、情報処理Xと称しました。情報という分野を超え、多くの領域と繋がる記事を増やそうという考えです。特集記事も専門的なテーマをとりあげようと難しく考えるのではなく、身近な分野でいかに情報が使われているかを知ってもらおうと考えました。
そこで参考にしたのが『月刊住職』です。私の心の支えでした。

『月刊住職』はすごいですよ。お寺がドローンをどう活用するかとか、お説教のヒントなど攻めた記事がたくさんあり、お寺と関係ない人が読んでも面白いです。参考にしてほしくて、編集委員会のみなさんにも読んでもらいました。
DXです。そのヒントとなったのが、日本ロボット学会誌のビデオ特集号です。紙だけではなく映像が伴うことでこんなに記事が立体的になるんだ、と思いました。活字は活字で大切にしたいけれど、それだけでは伝えきれない情報技術があります。活字だけでは伝わらない層に向け、発信できる機能が必要だと思いました。それがTwitterの活用や漫画の強化に繋がっています。
内部に向けては、Slack上でやり取りをする取り組みを行いました。塚本先生の時代は、1回の編集会議をとても丁寧にしていました。アンケートを1つずつ読んで3-4時間かけて議論するやり方です。それはそれで大切だと思いますが、私自身がそこまで時間を割けないので難しいと思いました。そこでSlackを学会誌の編集委員会で使ってみたのです。それぞれの分野や分科会、イベントごとにチャンネルを作成して、議論を進めました。

『情報処理』編集委員のSlackを展開
編集会議は月に1回行っていましたが、Slackならそれを待たなくても都度議論ができます。さらに意見を出しやすい環境を整えるという目的もありました。日本人は空気を読みすぎて、自分の質問でみんなの時間を奪ってしまっていいのかと思いがちです。Slackであれば気軽に発言できます。Skypeを利用してハイブリッドの会議を行うと、遠隔の参加者を置き去りにしがちでしたが、Slackでは意見が拾いやすくなりました。
「何のための学会誌か」と立ち返ると、日本語で議論できる、学べるメディアだと認識しています。それをどのようにして若い人に訴求できるかを考え、Twitterやnoteといった方法を選びました。DXを進めなくてはならないから始めたわけではなく、手段としてデジタル化を進めたわけです。
私はVR(バーチャルリアリティ)を研究していますが、何でもバーチャル化すればいいというのは乱暴すぎます。いかにバーチャルとリアル、サイバーとフィジカルとのバランスを考えられるか。これが研究者に求められるセンスです。


稲見先生の研究室には様々な実験品が置かれている
DXも同じです。何でもデジタル化すればいいわけではありません。さじ加減が大事です。目の前に学会誌があれば読んでくれます。紙の存在感があります。オンラインの記事は読みに行く必要がなければ読んでくれません。オンライン記事への動線をどうしていくかは課題です。
特集は「広げる記事」だからです。学会誌の読者以外の人にも読んでほしいからオンライン化しました。特集は外部と繋げる企画ですし、ソーシャルメディアで拡散されやすいです。一方、紙のほうが届くこともあります。研究室に1冊置いてあれば、みんなが回し読みしてくれますし、図書館に置いてあれば学生も手に取ってくれるかもしれません。さまざまな動線を作っておく必要があります。
多くの層に届けるため、コロナ禍前には技術書典(技術系同人誌を販売するイベント)で販売したり、コロナ禍ではバーチャルマーケットに出展したりしました。

技術書典で販売
社会やコミュニティの中で、情報処理学会というものの存在が見えるように意識したのです。社会から情報学は要らない、と思われたら困ってしまいますから。
以前、パリにあるパリ工芸技術博物館に行きました。そこにラボアジェの部屋があります。ラボアジェは質量保存の法則や酸素の存在を発見した科学者で、フランス革命の際にギロチンで処刑されてしまいました。裁判のとき、裁判官から「フランス革命政府には化学者とサイエンティストは要らない」と言われて処刑されてしまったらしいです。自分がそうなるかもしれないという危機感は持ったほうがいいと思いました。
我々研究者は、社会の中ではマイノリティです。社会の人々に研究内容が見えるようにして、社会にとって良いと思ってもらい続ける必要があります。そのために、学会の外側の人たちにも価値があると気づいてもらえるようにするのが編集長としての想いでしたし、私のライフワークでもあります。

副編集長時代から、編集長になったらどうやっていこうか考えていました。編集長になるまで出し惜しみしていたわけではなくて、副編集長時代から取り組んでいました。始まりはよく考えていましたが、終わらせ方は計画的に考えていたわけではありません。ただ、私の次の編集長は女性にやってほしいというのは計画的に考えていましたし、実際に、五十嵐悠紀先生が就任されました。
計画性という面で想定外だったのが、新型コロナウイルスです。コロナ禍に編集委員のみなさんのモチベーションを維持しつつ、魅力的な特集記事を出すことを意識していました。編集委員のモチベーションを上げることも編集長の仕事です。そこで大切なのが「ボケ力」です。「編集長が特集記事の企画で変なことを言ってるから、もっとこうしましょう。」というツッコミを誘います。これは研究においても大切です。若いときは「ツッコミ力」のほうが大切です。この問題、自分ならどうやって解決しようと考えるべきです。キャリアを積んでいくと、問いを立てることのほうが大切になります。だから学会誌の運営でも、まずは変なことを言い出すことから始めます。
あとは「関根勤力」も必要です。関根勤さんは、面白がるリアクションがとてもうまいじゃないですか。何か面白い提案があれば、きちんとリアクションして返してあげるのです。
これらは研究室の日常でもあります。そう考えると、編集は素人の研究者が、学会誌の運営をやる意味があるのかもしれません。つまり、研究でやってることの水平展開できることが、学会誌の編集業務であったわけです。
『情報処理』は、長い間読まれている教育的なコンテンツです。「情報」は今後入試科目に加わり、授業にも導入されるようになりました。ただし、勉強を入口に「情報」を学ぶようになると、取りこぼされた人が年少のころから「情報」を嫌いになってしまうのではないかと危惧しています。
私の場合、「情報」を学んだのは面白いゲームがきっかけです。当時『現代大戦略』というパソコンゲームがBASICというプログラミング言語で書かれていて、ストップキーを押すとソースコードが見られました。そのソースコードをいじると、爆弾の数を10倍にするような操作ができるのです。そうこうしているうちにソースコードの読み書きができるようになりました。ゲームでOJTをしていたようなものです。

誰かに「やれ」と言われてやったわけではなく、自分の意思なので勝手に覚えます。今まで情報処理学の中核にいた人たちは、多かれ少なかれそういう人が多いと思います。居ても立ってもいられない、もしくは作りたいものがあって、そのために「情報」が必要だから学んだはずです。それが勉強としてやらされてしまうと、何の役に立つかもわからないまま嫌いになってしまう可能性があります。数学や理科などで起きているように、小さい頃に「情報」アレルギーになってしまうのを懸念しているのです。
「情報」がどう楽しく自分に関わってくるのか、より良い人生を生きていくために使えるのか。こうしたことをイメージしてもらうために、学会誌は私たちが楽しんでいる背中をうまく伝えるような記事を増やしていくべきだと思います。例えば、最先端の研究者だけでなく、ジュニア会員(小学生~大学3年生)の学生が「情報」に取り組んでいる様子をとりあげてもいいと思います。人に焦点を当てる点は、私が編集長時代に積み残した、そこまで想定していなかったテーマです。学会誌『情報処理』が、「情報」に関心のある人の登竜門となるメディアになることを期待しています。
プロフィール
稲見昌彦 氏
東京大学 先端科学技術研究センター 身体情報学分野 教授・博士(工学)
総長特任補佐
情報処理学会フェロー、理事(企画担当)、各種委員会委員
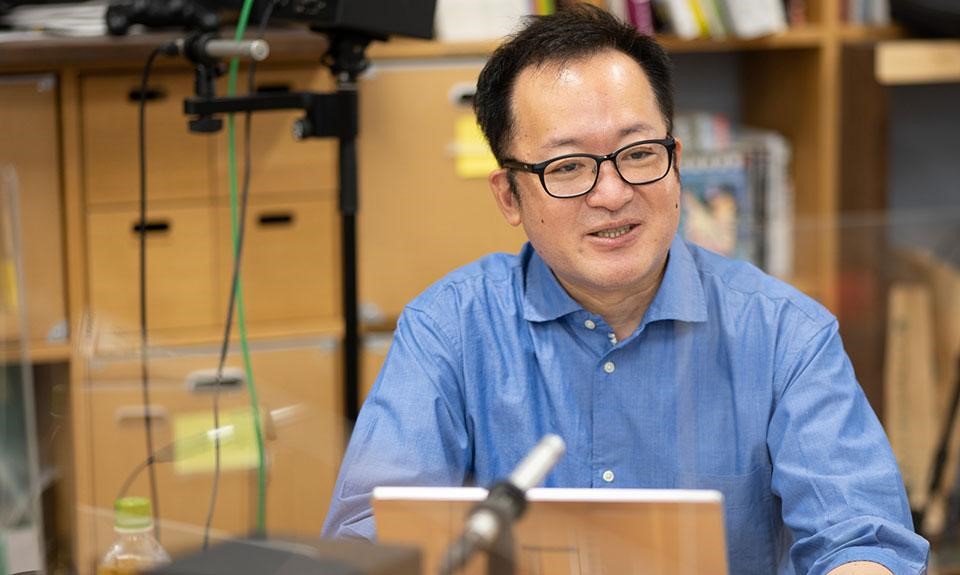
1999年 東京大学大学院工学研究科博士課程修了。博士(工学)。東京大学助手、電気通信大学教授、慶應義塾大学大学院教授等を経て2016年より現職。文部科学大臣表彰若手科学者賞、本学会山下記念研究賞、論文賞、長尾真記念特別賞などを受賞。超人スポーツ協会代表理事、JST ERATO稲見自在化身体プロジェクト研究総括、IPA未踏PMを兼任。本学会フェロー、日本VR学会理事・フェロー、日本学術会議連携会員。
インタビューは終始和やかな雰囲気で、ときに笑いも加わりあっという間の1時間でした。稲見氏はメタバース研究の第一人者ですが、研究にしても学会誌の編集長にしても、ベースは「楽しむこと」。そこに「ボケ力」と「関根勤力」が加わり、チーム力が強化されています。組織づくりの面でも多くの気づきをいただきました。
インタビュー実施日:2022年8月30日

取締役/執⾏役員
広富 克子
コンテンツマーケティング支援
神⼾⼤学経営学部卒業。住友ビジネスコンサルテイング株式会社⼊社。マーケティングリサーチ・コンサルティング業務を中⼼に活動し、その後AJS(オール⽇本スーパーマーケット協会)にて、プライベートブランドの商品開発・営業に従事。2003年10⽉、株式会社パワー・インタラクティブ⼊社。2006年4⽉、取締役執⾏役員に就任。全社営業戦略を統括する。

2024.04.08
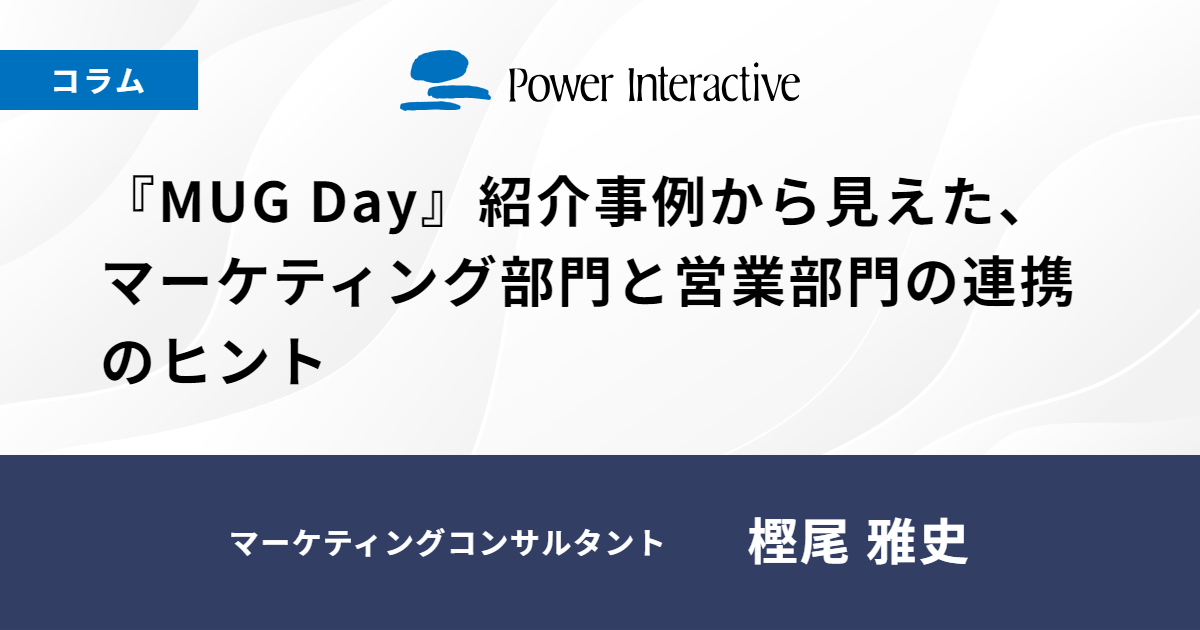
2024.02.13
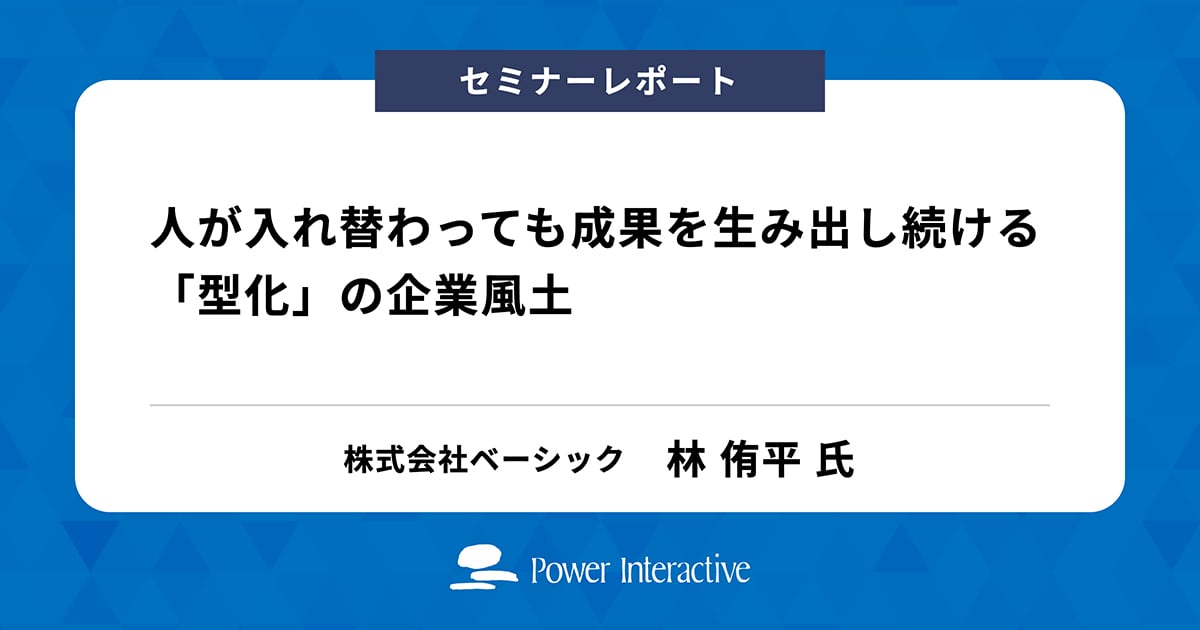
2024.02.08