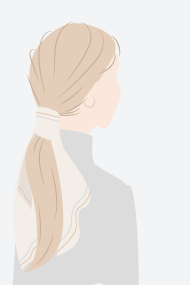「ユニファイドコマース」は、オムニチャネルの次世代、あるいはEコマースの進化形として、注目が集まっている概念です。
しかし、いまひとつ言葉の意味が理解しにくいと感じるかもしれません。たとえば、「オムニチャネルと何が違うの?」という声をよく聞きます。
本記事では、ユニファイドコマースを基本の知識から解説します。あらためて定義を押さえ、具体的にどう取り組んでいけばよいのか、考えるヒントとなれば幸いです。
ユニファイドコマースとは何か
さっそくですが、「ユニファイドコマースとは何か?」から見ていきましょう。
直訳は「統合された商取引」

ユニファイドコマースの「ユニファイド(unified)」には、〔統合された、一元化された〕という意味があります。
「コマース(commerce)」は、EC(electronic commerce:電子商取引)という言葉があるように、〔商取引〕という意味です。
ユニファイドコマースとは、直訳すれば〔統合された商取引〕という意味になります。
オンライン・オフライン問わず、あらゆる顧客データや業務データを一元的に集約し、商取引を展開する概念のことを、ユニファイドコマースといいます。
オムニチャネルとユニファイドコマースの違い
「統合化」というキーワードから、「オムニチャネル」を連想される方もいるかもしれません。
オムニチャネルの「オムニ(omni)」は〔全体の、すべての〕という意味を持ちます。
オムニチャネルの考え方では、あらゆる“販売チャネル”を統合して、顧客の利便性を高めるところに重点がありました。
オムニチャネルが目指した世界を簡単にいえば、「顧客が、ネットでもリアル店舗でも、便利に買い物ができる世界」です。
一方、ユニファイドコマースが目指すのは、チャネルはもちろんのこと、決済システム、カスタマーサービス、商品・サービス、顧客データ、販売管理、在庫管理などのすべてが、統合された世界となります。
ユニファイドコマースが重要な理由
なぜ「これからの時代はユニファイドコマース」といわれているのかといえば、3つのポイントが挙げられます。
- オンラインとオフラインを行き来するカスタマージャーニー
- 実店舗にもやってくる「パーソナライズ」の波
- 販売・在庫管理データの一元化の必要性
それぞれ見ていきましょう。
1. オンラインとオフラインを行き来するカスタマージャーニー
1つめのポイントは、現代のカスタマージャーニーは、オンラインとオフラインを、行き来しているからです。
カスタマージャーニーとは、顧客の一連のブランド体験を「旅」になぞらえた概念ですが、もはやオンライン・オフラインの壁はなくなっています。
とくに、モバイルデバイスの普及によって、その傾向は顕著となりました。
たとえば、実店舗に訪れた顧客は、スマートフォンを片手に、商品の評判をチェックしながら買い物をしています。
店舗で実物をチェックしてから帰宅し、ネットショップでポイント付与率の高い日に購入する顧客もいます。
顧客自身が、オンライン・オフラインをシームレスに動き回っている現実が、すでにあるのです。
そんな顧客たちへ、どのタッチポイント(顧客接点)でもベストな体験を提供するためには、企業側もシームレスになることが不可欠です。
ユニファイドコマースによって、統合的なアクションを起こせるようにしなければなりません。
2. 実店舗にもやってくる「パーソナライズ」の波
2つめのポイントとして挙げられるのが「パーソナライズ」です。
パーソナライズとは、デジタルテクノロジーを活用することで、顧客一人ひとりに最適化したマーケティングコミュニケーションを実現する手法です。
よく知られているパーソナライズとして「レコメンド」があります。その人の興味関心や行動履歴に合わせて、最適なおすすめが表示される機能です。
エンタメコンテンツを楽しむときも、ネットショッピングをするときも、「自分に合う情報が、自動的に表示されている環境」が、私たちの日常になりつつあります。
やがて、オフラインの環境下でも、自然とそれを求めるようになるでしょう。
オフラインでも、オンラインと同じようにパーソナライズを実現するために、ユニファイドコマースへの移行が進むと考えられます。
3. 販売・在庫管理データの一元化の必要性
オフライン・オンラインを自由に行き来するカスタマージャーニーや、あらゆるシーンでのパーソナライズを実現するためには、ITシステムが一元化されていることが必須となります。
販売管理や在庫管理のデータが一元化できていなければ、企業は大変なコストと労力を奪われることになるからです。
ユニファイドコマースによって、統合的にひとつの場所でデータを管理することで、企業は効率的かつ生産的に、業務を遂行できます。
ユニファイドコマース実現のヒント
ユニファイドコマースは、よりよい顧客体験を創出し企業が成長するために、重要なカギとなります。
では、これからどう実現していけばよいのでしょうか。3つのヒントをご紹介します。
- 社内チームの統合
- プラットフォームの統合
- ロイヤルティプログラムの統合
1. 社内チームの統合
まず挙げたいのが、少し意外なポイントかもしれませんが、社内チームの統合です。
多くの企業では、販売チャネルごとにチーム(部署)が分かれています。
たとえば「ECチーム」「店舗チーム」「コールセンター」という具合です。チーム同士を競争させることで、成長を促しているケースもあるでしょう。
しかし、ユニファイドコマースにおいては、チームの分断は、顧客体験に悪影響を及ぼす可能性があります。顧客の購買行動を奪い合うことで、自然なカスタマージャーニーをねじ曲げるリスクが生じるためです。
「ECでも、店舗でも、電話でも、顧客にとって都合のよい方法を、いつでも自由に選択できる環境」を、従業員が一丸となってサポートできる組織体制が必要です。
2. プラットフォームの統合
次のポイントは、プラットフォームの統合です。
これまではバラバラだったITシステムを、ひとつの集中型のプラットフォームに置き換えることは、ユニファイドコマースに必須となります。
EC、店舗売上、受注処理、在庫管理、顧客関係管理(CRM)、その他のあらゆる業務やデータを、一元的に管理します。
といっても、新たなシステムを慌てて導入することは、おすすめできません。まずは既存のプラットフォームと業務プロセスを、綿密に精査するところから始めます。
システムの入れ替えを行う場合は、信頼できる専門性の高いパートナー企業を選定し、十分な時間とリソースをかけて進行することが大切です。
システム面でのつまずきは、長期にわたって企業の経営に影を落とす危険が大きいためです。
「どんな心構えでシステムと向き合うべきか?」については、2022年7月に経済産業省が公表した「DXレポート2.2(概要)」の「デジタルで収益向上を達成するための特徴」が示唆に富んでいます。
以下は引用です。


3. ロイヤルティプログラムの統合
最後に、3つめはロイヤルティプログラムの統合です。
ロイヤルティプログラムとは、自社ブランドを継続的に購入するロイヤルティの高い顧客に報いるための仕組みを指します。
購入回数に応じてランクアップする会員制度や、ポイントやクーポン券の付与は、ロイヤルティプログラムの一種です。
今すぐのユニファイドコマース実現が難しい企業でも、ゆくゆくは到達することを見据えて、ロイヤルティプログラムを設計しておくとよいでしょう。
たとえば、実店舗とECサイトで共通のクーポン券を使えるようにする、SNSでのエンゲージメントに対して、実店舗での特典をつける、といった具合です。
オフラインとオンラインを行き来する顧客の行動に、ロイヤルティプログラムを最適化することが、ユニファイドコマースの基盤づくりにつながります。
さいごに
本記事では「ユニファイドコマース」をテーマにお届けしました。
最近では、オフラインで受け取る商品・サービスを、モバイルオーダーで事前注文・支払いできるサービスが、身近に増えてきました。
たとえば、スターバックスの「モバイルオーダー&ペイ」や、タクシーアプリGOの「GO Pay」などです。
今後、この流れは加速し、ユニファイドコマースが商取引のデフォルトとなるのも、時間の問題かもしれません。自社ブランドではどう適応できるか、検討してみていただければと思います。
*1:出所:経済産業省「DXレポート2.2(概要)」p12-13